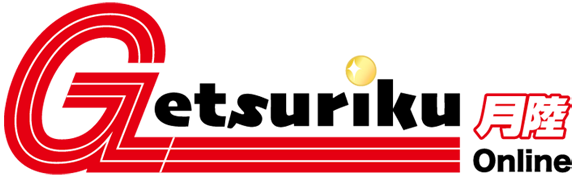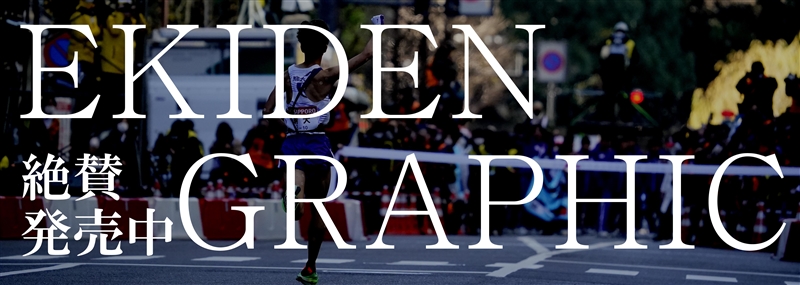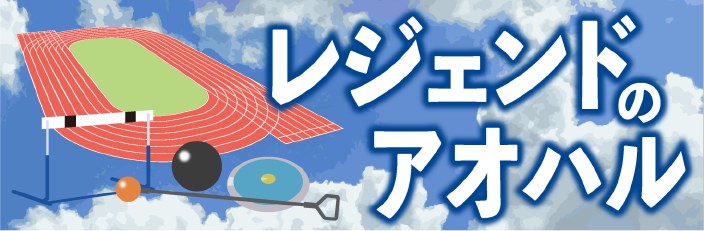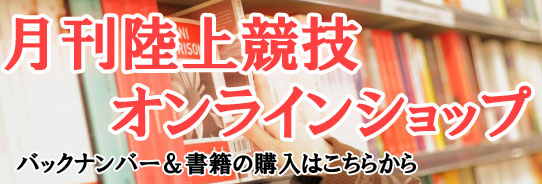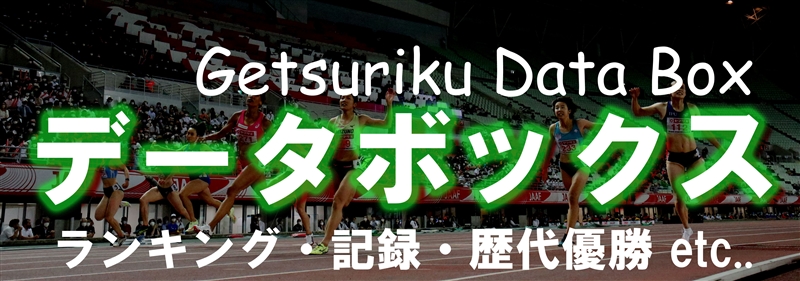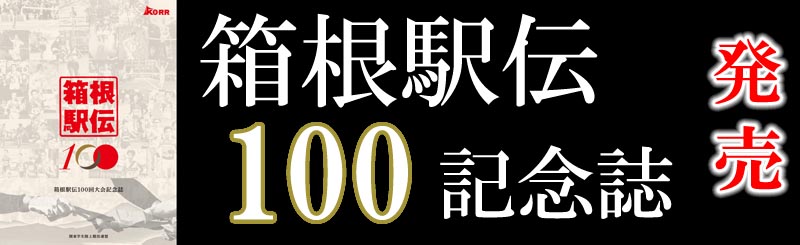日本陸連は10月30日、9月に行われた東京世界選手権の総括会見を開き、有森裕子会長、田﨑博道専務理事が登壇した。
日本陸連創設100年の節目に迎えたビッグイベントに対し、「その成功が今後の陸上界の成長、発展につながる」(田﨑専務理事)として、力を注いだ。
有森裕子会長は、6月に就任後から間もなく迎えたビッグイベントについて、「本当に夢のような大会だった」と振り返る。
自身としては、大会を主催する世界陸連(WA)理事として役割をこなしながら大会期間中を過ごしていたという。また、34年前の1回目の東京世界選手権の時には選手として出場し、女子マラソンで4位に入った経験もある。「現役時代の感覚と、自分自身の立場が混在したような感じで観ることになった」と注釈を付けつつ、世界中から集まったトップアスリートたち、日本代表選手たち、観客、大会運営やボランティアをはじめとした支える人たちなど、「一人ひとりが人間として感動するような場面を、9日間作って来られた」と賛辞を送った。
田﨑専務理事も、「開催国のNF(ナショナルフェデレーション)という立場で世界陸連、東京2025世界陸上財団と密接な連携に勤めながら、競技運営、機運醸成などを進めてきた」とし、「コンペティションディレクターからは『素晴らしい運営だった』という評価を受けた」と明かす。
日本陸連としても大会のPR、ファンエンゲージメントなどさまざまな機運醸成への取り組みを「一体的に、波状的に」行ってきた。その中で、「期待していたほどのレベルに至らなかった」もの、「一体感ある空気が作れた」ものの両面がありつつも、約62万人の観客集客につながったことを評価する。
今後は、「この経験を最大化していくこと。この経験、体感を無駄にしないこと」(有森会長)が目標となる。
選手たちに対しては「これからいかに、国内だけに世界にチャレンジし、体感・体験できるのか」を課題に挙げ、「それを組織としてどうつなげていくのかが大事なこと」と言う。
「初出場の選手もかなりいましたが、国内での経験が多いと、自分らしく競技する、自分のペースで競技するという経験が多くなる。でも、世界の大会においては自分らしくやったとしても、勝負につながらないと意味がないという体験をした選手が多かったのではないか。自分の競技をどう感じ、どう評価していくかが大事になってきます」
日本陸上界としては、来年の名古屋アジア大会、2027年の北京世界選手権、2028年のロサンゼルス五輪を「一貫したプログラム、一つとのストーリーとして進めていくことが大切」と田﨑専務理事。スタジアムの熱狂をいかに生み出していくかは「メディアだけではく、ファンからの発信も高めないといけない。そういった風土を作り上げていく」必要性を説く。
競技運営に関しても、「国際基準に照らし合わせた審判基準の再設計や、審判の育成」を目指しつつ、日本らしい正確な競技運営と、世界陸連が目指したエンターテインメント性のある競技運営を、いかに両立させるかを課題に挙げる。もちろん、「国内大会それぞれの条件を踏まえたうえで、何を目的にするか、何を持って成功とするか」は各大会による。それでも、「それぞれの大会が目指す価値を追求していく。その積み重ねたが陸上の発展につながる」とした。
有森会長、田﨑専務理事ともに「今回の経験を生かして、つなげていきたい」と口をそろえる。東京世界選手権で生まれた熱狂を、未来へ。それが今後の日本陸上界の大きな課題となる。
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking  人気記事ランキング
人気記事ランキング
2026.01.31
田中希実が米国の室内800mで2分04秒32!26年トラック2戦目は2年ぶり自己新
-
2026.01.30
-
2026.01.30
-
2026.01.29
-
2026.01.25
-
2026.01.18
-
2026.01.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2026.01.31
ダイソーが都道府県男子駅伝で8位までのトロフィーを授与「平和の花カンナ」モチーフ、平和記念公園の折り鶴を再活用
株式会社大創産業は1月18日に行われた全国都道府県対抗男子駅伝において、優勝した宮城をはじめ8位までに入賞したチームにトロフィーを授与したことを発表した。 この取り組みは2019年にスタートし、コロナ禍で大会が中止となっ […]
2026.01.31
田中希実が米国の室内800mで2分04秒32!26年トラック2戦目は2年ぶり自己新
1月30日に米国・ボストン大で行われた室内競技会女子800mで、田中希実(New Balance)が2年ぶり自己新となる2分04秒32をマークした。 3組タイムレースの2組に入った田中は、トップと2秒36差の6着でのフィ […]
2026.01.31
クレイ・アーロン竜波が800mショート日本新・アジア新の1分45秒17!米国室内で快走 石井優吉も自身の記録上回る1分46秒41
米国ペンシルベニア州のペンシルベニア州立大で行われたPSUナショナルオープン(室内)の1日目(1月30日)、男子800mでクレイ・アーロン竜波(ペンシルベニア州立大)が1分45秒17のショートトラック日本新・アジア新記録 […]
2026.01.30
順大・吉岡大翔、駒大・谷中晴、中大・岡田開成、創価大・小池莉希らが欠場/日本学生ハーフ
1月30日、日本学連は2月1日に開催される日本学生ハーフ選手権の欠場者リストを発表した。 主な欠場者では吉岡大翔(順大)が出場を見送り。吉岡は1月2日の箱根駅伝で2区を走った後、10日に米国フロリダ州で開催された世界クロ […]
Latest Issue  最新号
最新号

2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝